プロテイン製品の表示基準を解説/アレルギーや栄養成分の重要ポイント
- サービス フードガイド

- 2025年5月19日
- 読了時間: 6分
更新日:2025年12月11日

■目次
■そもそも“プロテイン”とは?〜表示ルールを学ぶ前に知っておきたい基本知識
プロテイン(protein)とは、日本語で「タンパク質」を指し、骨や筋肉、血液など、私たちの身体に欠かせない重要な栄養素です。
タンパク質は、肉や魚、卵類などさまざまな食材に含まれ、日本では、特にタンパク質を主成分とした栄養補助食品を「プロテイン」と呼んでいます。これらは、主に牛乳や大豆などの食品からタンパク質を抽出し、パウダー状に加工されたものが多くありますが、最近では、ゼリーやドリンク、お菓子感覚で食べられるバータイプのものも登場しています。
■プロテインラベルでよく使われる名称を理解しよう
食品表示基準では、一般加工食品に一般的な名称を記載することが定められています。一般的な名称とは、その内容を表す誰が見てもわかる社会通念上一般的な名前です。商品名ではありません。
プロテインを加工した食品では、以下のような名称が見られます。
<プロテインの名称:例>
・プロテインパウダー(タンパク質加工食品)
・プロテインパウダー(粉末たんぱく飲料)
・プロテインパウダー(粉末清涼飲料水)
・乳たんぱく加工食品
・栄養調整食品(たんぱく含有食品)

■表記において「高タンパク質」とは何を意味するのか?表示のカラクリ徹底解説
たとえパッケージの商品名に「プロテイン」と表示されていても、必ずしも高タンパクであるとは限りません。
消費者庁の「事業者向け食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン」では、
「高い、低いに言及せずに栄養成分名のみ目立たせて表示するものについては、栄養強調表示の規定は適用されません。
ただし、当該規定を満たしていないにもかかわらず、文字の色や大きさ等によって目立たせた表示をすることは望ましくありません。消費者に誤認を与えないような表示をする必要があります。」と記載されています。
つまり、プロテインという名称や商品名は、原材料に使用していれば記載できますが、実際の含有量が低い場合、誤認を与えないよう注意する必要があります。
<プロテイン誤解を招かない対策例>
1. 目立たせない表示方法
商品パッケージや広告において、タンパク質含有量を強調するような文字の色や大きさを控えることが重要です。消費者が誤解しないように、目立たせない表示方法を取ることで、「高タンパク」などの印象を与えないようにします。
2. 明確な栄養成分表の表示
栄養成分表において、タンパク質の含有量を明確に示し、1食あたりや100gあたりの数値を具体的に記載します。このように数字で具体的な量を示すことで、消費者が実際の含有量を確認でき、誤解を避けられます。
3. 「プロテイン」という用語の適切な使用
商品名に「プロテイン」という言葉を使う場合、そのタンパク質含有量が低すぎると誤解を招く可能性があるため、タンパク質を多く含む製品に限定して使用することが推奨されます。また、もしタンパク質の含有量が低い場合には、製品名に「プロテイン入り」「タンパク質含有」など、具体的な表現を使うことで、誤認を防ぎます。

■「たんぱく質豊富」はいつ使える?法的基準と表示上の要件
主に食品からタンパク質を抽出した原材料が主材料の食品には、「プロテイン」などの表記が可能ですが、食品表示基準では、一般加工食品及び生鮮食品に栄養素に「含む」や「高い」などと表記する場合には、指定された分析方法によって求められた値(※)が定められた基準を満たす必要があります。
タンパク質の場合、以下のような基準があります。
※タンパク質の場合、窒素定量換算法と定められています。
※( )内は、一般に飲用に供する液状の食品 100ml 当たりの場合
■見落としがちなアレルゲン表示ルール
プロテイン製品は、原料に応じてアレルギー反応を引き起こすリスクがあります。食物アレルギーは、卵や牛乳などのタンパク質を体内で異物として認識し、抗体が過剰に生成されることで発症します。特に日本では、牛乳由来のホエイプロテインやカゼインプロテイン、大豆由来のソイプロテインが一般的に流通しています。
特に牛乳アレルギーは発症例が多く、牛乳由来の製品にはアレルギー表示が義務付けられています。また、大豆アレルギーの可能性も考慮し、原料を確認することが重要です。
<食物アレルゲンの表示が義務化・推奨されている品目>
表示義務 | 対象食品 | 区分 | |
特定原材料 (8品目) | 義務 | 小麦、卵、乳、えび、かに、そば、落花生(ピーナッツ)、くるみ(※) | 発症数が多く、重篤度が高いもの |
特定原材料に 準ずるもの (20品目) | 推奨 | カシューナッツ、アーモンド、豚肉、牛肉、あわび、いか、いくら、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、りんご、もも、オレンジ、キウイフルーツ、マカダミアナッツ、やまいも、ごま、ゼラチン | 症例数や重篤な症状を呈する者の数が、特定原材料に比べると少ないもの |
※くるみは現在、経過措置期間。2025年の4月から表示が義務化。

■賞味期限・消費期限の違い+表示のルール
期限表示には「賞味期限」と「消費期限」があります。賞味期限は未開封かつ適切な方法で保存した場合に比較的長期間品質が保たれる食品に記載されます。一方、消費期限は未開封でも急速に品質が劣化する食品に記載されます。未開封のプロテイン製品には多くの場合、賞味期限が表示され、開封後は早期の消費が推奨されます。
■プロテインの表示ラベル作成において注意すべきチェックポイント
本記事ではプロテイン製品の表示基準を解説しましたが、食品表示はすべての食品において重要です。法律に基づいた正確な情報を提供し、消費者が安心して選べる商品づくりを心がけましょう。
※この記事に掲載されている情報を利用する際には、お客様自身の責任で行ってください。
※本記事の情報は公開時や更新時のものです。現在の状況や条件と異なる場合があります。また、記事の内容は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
執筆者

管理栄養士:横川仁美
食専門ライター×Nadiaアーティスト(料理研究家)
管理栄養士・横川
保健指導を中心に述べ2500人の食のアドバイスに携わる。食事・栄養・食材のコラム執筆・監修、レシピ作成を中心に活動、薬機法・景品表示法・健康増進法・食品表示法の知識を活かし、企業の記事作成や商品オリジナルレシピ開発に携わる。
<参考文献>
・財務省「「ファイナンス」令和6年2月号~内容紹介~(日本における健康食品の成長性)」
・消費者庁の「事業者向け食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン」
・加工食品の食物アレルギー表示ハンドブック(事業者用)(令和5年3月)
最終更新日:2025年7月16日
.png)

.png)
.png)


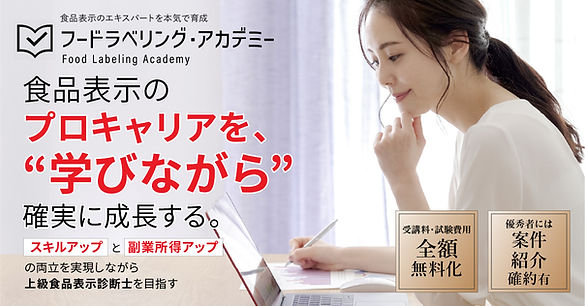

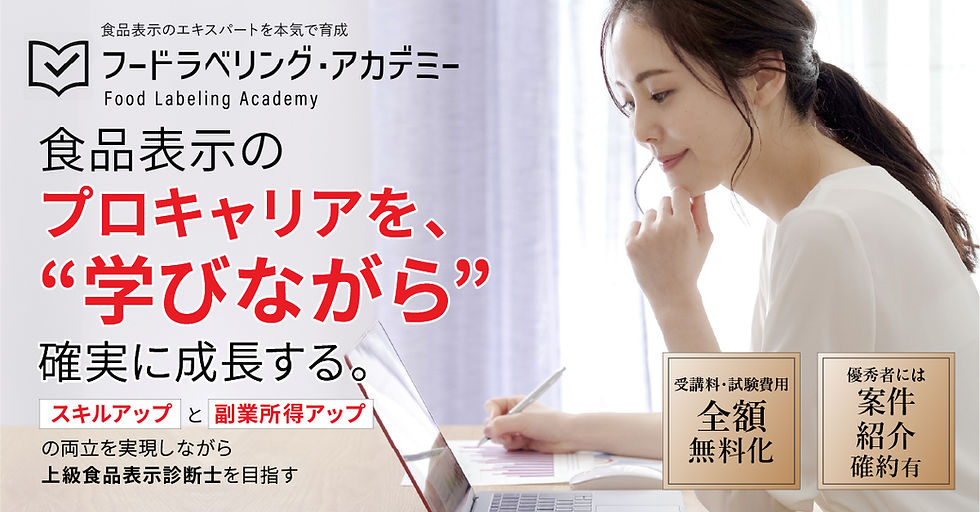



コメント